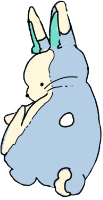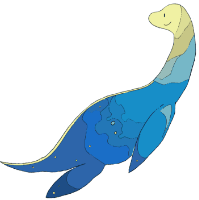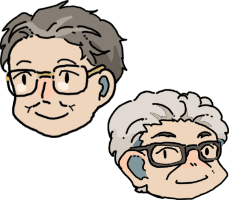Miscellanea(雑)
英語大百科カテゴリー

Miscellanea
雑

カテゴリー:Miscellanea(雑)の最新の単語

英語大百科の単語ランク
ランクを選択して単語を見つけよう
「英語大百科」では、「ヨーロッパ言語共通参照枠」(通称CEFR)の6段階区分に準じて作成した基準表に従ってC2~A1の記号で表しています。
英語大百科のカテゴリー
好きなカテゴリーを選択しよう
英語大百科の監修者Navigators

ナビ1号山田 雄一郎
広島大学教育学部大学院修士課程修了。もと広島修道大学教授。主な著作:「言語政策としての英語教育」(渓水社)、「英語教育はなぜ間違うのか」(筑摩書房)、「日本の英語教育」(岩波書店)、「外来語の社会学」(春風社)、「英語力とは何か」(大修館書店)、「小学生からの英語絵辞典」(研究社)、「英単語QUEST 2000」(学研プラス)

ナビ2号佐伯 一行
英語能力テスト開発研究所(IQELT)代表。京都外国語大学専攻科修了。中学校英語教師、学習塾経営、日本英語検定協会顧問、大学非常勤講師、東京書籍顧問、IELTS公式テストセンター顧問を歴任。英語に関する各種研究会の企画運営を通して英語教育界に広く知己を得る。米国、イギリス、フィンランド、シンガポール、中国、韓国などでの学会や研究会への参加を重ねる。
- 英語大百科
- カテゴリー:Miscellanea